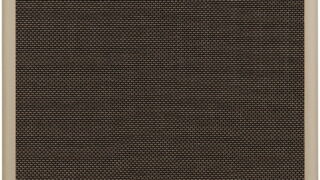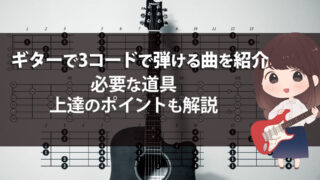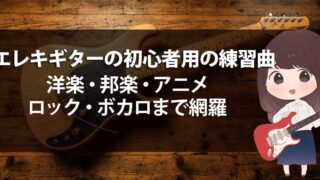本稿初稿執筆時の2021年12月31日は、大みそか。
大みそかといえば、何を思い浮かべるでしょうか。除夜の鐘、年越しそば、新年カウントダウン…。
そして、年末の風物詩である、NHKの紅白歌合戦。
ところが、この紅白歌合戦、ギタリストやベーシストをはじめとした楽器プレイヤーにとっては、何とも言えぬ違和感を覚えながら見ているのではないでしょうか…。
いえ、紅白だけではありませんね。ミュージックステーションなど、テレビにおける多くの音楽番組に対しても、同様だと思います。
その理由は、楽器が実際に演奏されず、ミュージシャンが弾いている振りをしているだけの、いわゆる「当て振り」になっていること。
本日は、そんなテレビにおける音楽番組の「当て振り」事情に迫りたいと思います。
- 音楽番組の演奏が生演奏だと思っていた
- 「当て振り」という言葉の意味を調べていた
- 演奏者が当て振りのことを実際どう思っているのかを聞いてみたい
- 「当て振り」をどのようにして見抜けばいいのか、教えてほしい
- なぜ音楽番組の収録で当て振りが横行しているのかを知りたい
- 生演奏の音楽番組は、当て振りと何が違うのかを知りたい

もくじ
音楽番組における「当て振り」とは
まず、そもそも「当て振り」とは何なのか、定義付けをしておきましょう。
「当て振り」とは、音楽番組の収録に際して、ギターやベース、ドラム、バイオリンなどといった楽器の音を、実際にその場でなされる演奏ではなく、あらかじめ録音していた音源を流すことで対応するともに、演者はそれに合わせて演奏したふりをする行為のこと。
つまり、音楽番組に登場するバンドのギタリスト・ベーシスト等は、一切演奏することなく、音源にあわせて、カメラの前で「弾いているふり」をしているだけ…ということなのです。
楽器演奏のプロとして生き、それを生業としている者にとって、「音に合わせて演奏しているふりをする」という行為は、なかなかに屈辱的ではないかと個人的には思うのですが、テレビ音楽番組では、長きにわたってこの「当て振り」による収録が恒常化しています。

「エアギター」と「当て振り」は全く違うものです
なお、類似の行為として「エアギター」等を挙げる人がいますが、これは違います。
エアギターは、「演奏しているふりをしている」ことを前提に、その「演奏しているふり」の態様を楽しむ芸ですので、あたかも演奏しているかのように聴衆を錯覚させようとする「当て振り」とは、全く異なるものです。
なぜ「当て振り」をしないといけないのか
さて、先ほど少し触れたように、「自分の生演奏ではなく、演奏したふり」を聞かせる当て振りは、プロのプレイヤーにとっては、心底不本意なことではないかと拝察しています。
この点、多くのミュージシャンは、内心思うところはありつつも、「大人の事情」で黙っているのかなあ…というふうにも勘ぐってしまうのですが、最近はSNSの活用によって、少し踏み込んだことをしゃべってくれるミュージシャンの方も増えました。
昨日のテレビ、感想をありがとう。
見事な当てぶりだっただろう?— ハマ・オカモト (@hama_okamoto) August 3, 2014
生演奏という名目でのアテブリが今は主流ですね。ライブに通う人にとったら、そんなもん1発で見抜けますよね。まずみんなアンプの電源はいってないし、シールド刺さってないし。昨夜のOKAMOTO’Sは楽曲の構成上の理由やら諸々で、初めてアテブリしてみました。
それはそれで楽しかったです。— ハマ・オカモト (@hama_okamoto) August 3, 2014

と、このように、多くのミュージシャンに思うところがあるにもかかわらず、なぜテレビの制作現場は、それを承知で「当て振り」をさせるのか。
一般には、次のような理由が考えられます。
演奏ミスのリスク回避
生演奏にはミスがつきもの。これはたとえどんなプロであっても同様です。
正確な演奏を売りにするプレイヤーももちろんいますが、それとてミスの可能性を完全にゼロにすることはできません。
とりわけ、ピアノが全面に出てくる楽曲や、バンド演奏におけるドラムなどについては、ミスの内容如何によっては、楽曲全体が大きく崩れてしまうことになります。
テレビ番組を完璧に仕上げたいと考える制作者にとっては、こうした「演奏ミスのリスク」というものを確実に回避できる当て振りは、非常に都合が良いわけなのです。
もっとも、こういった「演奏ミス」も含めてライブの醍醐味だと考えることもできますので、そこを過度に避けるようなやり方は、潔癖症っぽくて、個人的には「なんだかなあ…」と思ったりもしています。
機材トラブルのリスク回避
先ほどの「演奏ミスのリスク回避」とはまた別の視点における「リスク回避」がこれ。ライブにおけるトラブルで非常に多い、機材トラブルの話です。
ギターの音が出ない、PAのミキシングがうまくいかない、謎のノイズが乗ってしまう…。こういった、ライブのときによくある機材トラブルは、当然、音楽番組の収録で生演奏を行おうとしても、当然に起こってしまうもの。
「演奏ミス」はライブの醍醐味としておおらかに許すことができたとしても、音が出なかったり変な音が出たりする機材トラブルは、さすがにそうもいかないでしょう。
テレビ放送をNGなしで乗り切ることを至上命題とする制作者サイドにとって、この機材トラブルを未然に防げる当て振りは、非常に魅力的なわけなのです。
機材セッティングの時間・コスト削減
先ほどの「機材トラブル」の話とも少し関係しますが、機材を確実に音が出るように正確にセッティングするには、それなりの時間がかかりますし、時間がかかるということはそれに見合った人件費も必要になります。
通常のライブであれば、1つのバンド・ミュージシャンに対する機材セッティングを終えた後、ワンマンライブであれば2〜3時間、対バン方式のアマチュアバンドでも30分間はその設定を維持することができるわけですが、1〜2曲で出番を終えてしまう音楽番組の場合、そのつどセッティングを切り替えるというのは、相当に大変で、時間的にも金銭的にも消費するものが大きくなってしまいます。
特にテレビ業界が経営的に苦境に見舞われている昨今、少しでもコストカットをしたいと考える制作者にとって、こうした機材セッティングの時間・コストを削減しながら、多くのミュージシャンを「とりあえず」出演させられる当て振り方式は、非常に都合が良いのです。

バックバンドのコスト削減
出演者だけで演奏が完結するロックバンドであればいざ知らず、たとえばソロミュージシャンが生演奏をしようとすると、バックバンドのメンバーを同行させる必要があります。
しかしながら、このバックバンドのメンバーにも、当然人件費が発生します。
また、ホーンセクションや大規模ストリングス隊を編成するような楽曲の場合、そこに集まる出演者の人数も多くなることから、制作者サイドは楽屋の確保等といったロジスティクス面においても気を遣わなければならず、これもコスト発生要因となります。
こうしたコストを削減し、最小限の人員で効率良く番組収録を進める点においても、当て振りは非常に都合が良いのです。
「当て振り」を見抜くポイント
このように、「当て振り」というものは、基本的には完全に番組制作者サイドの都合のみによるものであり、そのステージで「演奏するふりをさせられる」プレイヤーにとっても、そして何より「ミュージシャンが奏でる音楽を楽しみたい」と考える視聴者にとっても、物足りないものになってしまいます。
さて、そんな「当て振り」、テレビ制作者的にはこれで視聴者の目をごまかせると思っているのかもしれませんが、ある程度楽器経験のあるプレイヤーなら、割と簡単に「当て振り」を見抜くことが可能です。
以下、当て振りを見抜くポイントを、列挙していきますね。
ギター・ベースアンプの電源ランプがついていない
マーシャルやフェンダー、メサブギー等のギターアンプがそこにセットされているにもかかわらず、どうも電源ランプがついている形跡がない…。
電源の入っていないギターアンプから、音が出るはずなんてありませんもんね。
どんな家電製品の説明書の「こんなときは?」で「動かない」の項目を見たときに、真っ先に確認を求められるのが「電源は入っていますか?」です。
電源の入っていないアンプなんて、完全に単なる雰囲気作りの小道具でしかありません。テレビにそんなものが映っていたら、まずは当て振りを疑いましょう。

ギターアンプの前にマイクがない
通常、エレキギターの音は、アンプの前にマイクを立て、その音をミキサーに送り込んで流す…というのが、PAにおける基本です。
ところが、テレビの音楽番組を見ていると、ギターアンプこそ置かれているものの、その前にマイクが立てられていない状況がほとんどです。
これもまた、当て振りを疑うべきファクターの1つになります。
ちなみに、ベースの場合、アンプの音を拾わずに、DIからミキサーに音を送っていることも多いので、ベースアンプの前にマイクがないことは、必ずしも当て振りを疑う要因にはなりません。
また、ギターであっても、最近はハイエンド系のマルチエフェクター・ギタープロセッサーの音をPAに直接送っているパターンも多いので、アンプの前にマイクがないことは必ずしも当て振りを意味しなくなってきた面もあります。
ギタリストの周りにシールドやエフェクター類がない
機材関係でいうと、特にギタリストは、数多くのエフェクターを用いていたりすることが多く、実際に演奏するときにもある程度を足下に置いていたりするもの。
ところが、当て振り収録現場の場合、そうしたエフェクターが足下に置かれていないどころか、何ならシールド(ケーブル)がエレキギターやギターアンプに刺さってすらいないこともよくあります。
「いやいや、最近はワイヤレスが普及してるから」という話もありそうですが、さすがにワイヤレスであってもエレキギターには短いシールドなりトランスミッターなりが刺さっていますし、「音の出口」であるアンプには何かしらのシールドが刺さっていないとおかしいです。
このあたりも含め「アンプが単なるオブジェ化している」という状況があれば、それはもう完全に当て振りだと言って良いでしょう。
弾き方と、実際に鳴っている音が違う
これは当該楽器のプレイヤーであれば一目瞭然かもしれませんね。「その弾き方で、そんな音が出るわけないよ」という状況があれば、完全に当て振りです。
たとえば、ギターソロでかなりの早弾きの音が鳴っているのに、テレビに映っているギタリストの手の動きが妙にスローだったり、ベーシストが左手を思いっきりスライドさせているのに、実際のベースラインは8分音符を淡々と刻んでいたり…。
また、ここまで分かりやすいものでなくても、たとえば押弦している場所と実際に鳴っている音が違う、とかもよくあります。
演奏経験のない人はだませるかもしれませんが、演奏経験のある人はこのあたり、かなりの違和感を持ちながら見ていることでしょう。

ドラムセットが明らかに普段と違う
ドラム関係で言うと、一番分かりやすいのがこれ。
プロの第一線で活躍するドラマーともなると、数多くのタムが並べられていたりツーバスだったりと、さまざまな個性がドラムセットの中から見え隠れするところなのですが…
そんなドラマーが、音楽番組に登場したときに、妙にシンプルなドラムセットの前に座っている。
これは完全に当て振りのパターンです。
少し前の話ですが、SIAM SHADEが2016年の日テレ系「THE MUSIC DAY」に出演したとき、ドラマーの淳士さんの前に置かれていたものが、シンプルなドラムセットだったことは、ファンの間でも物議をかもし、ネットニュースになったりもしていましたね。
SIAM SHADEが「THE MUSIC DAY」初出演 淳士の「エアドラム」が話題に – ライブドアニュース
ドラムの周りにマイクがない
通常、ドラムを演奏するときは、ドラムの周りにマイクを立て、その音をミキサーに送る…というのが一般的なPAのパターンです。
ところが、先述の「ギターアンプの前にマイクがない」と同様に、ドラムにおいてもこのマイクが省略されていることが多く、これもまた、当て振りを強く疑わせる要因になります。
演奏が完全にCDと一緒で、ライブ感がない
多くの場合、当て振りで用いられているときの音源は、CDに収録されたものと同じです。言うなれば、シングルCDによくある「カラオケ・バージョン」のようなものですね。ボーカルだけ抜かれた楽曲のサウンドです。
で、このCDに収録された演奏は、当然にしっかりとしたものになっており、またエンジニアの手で完璧にマスタリングされておりますので、演奏面でも音質面でも、非常によく整ったものになっています。
でも…それゆえに、ライブ感特有の空気感というか、グルーヴ感というものが、完全に失われてしまっているのです。
1回1回の演奏で、微妙に異なるニュアンス、ほんのわずかなリズムの揺らぎ、その時の気分なども含まれたアドリブのギターソロ、その瞬間の感情を込めたバイオリンの音色…こういったものが、当て振りの音楽番組では、一切感じられないのです。

最近は「口パク」も多い…
とはいえ、バンドやソロシンガーの「当て振り」は、ボーカルだけは生歌を披露しているところで、かろうじてライブ感を最後の最後でギリギリ残している…といえなくもありません。
最近の音楽番組では、当て振りに加えて悪目立ちするようになったのが「口パク」。歌までもを収録済みの音源を流して、本人は口をパクパクさせて、歌ったふりをしているだけ、というものです。
口パクについては、ダンスを取り入れたシンガーの場合、激しいダンスによる呼吸の乱れで歌が歌えなくなってしまうため、ライブパフォーマンス全体の質を確保する観点で、ダンスを優先して歌を口パクにする、といった事情もなくはないのですが…
一方で、音源をリリースする際にマスタリングの中で歌声を調整しすぎて、実際には音源どおりに歌えないシンガーが口パクでテレビに出演する、といった事態も横行しています。
口パクについては、当て振り以上に世の中的には厳しい目が向けられており、たとえばアメリカでは「『ライブ』と言っていながら実際に歌っていないのは詐欺的だ」と、多くの歌番組でこれが禁止されていたり、ライブで口パクをするとファンから非難を受けたりするようなことになっています。
昔の音楽番組は生演奏だった
ところで、こうした「当て振り」というのは昔から行われてきたかというと、そうではありません。
昭和の歌番組などを見ていると、歌手の後ろにバックバンドが控えていて、生演奏とともに歌っていたり、またバンドについても生演奏で出演することが当たり前になっていました。
たとえば、「8時だヨ!全員集合」の名物コーナー、ドリフの早口言葉では、あのバックのBGMが、バンドメンバーによる生演奏でした。
生演奏の「ゆらぎ」があるからこそ、ダンスにも、早口言葉にも心地よいグルーヴ感が生まれている…そんなふうに感じます。

【まとめ】音楽番組に「生演奏」の温かみが欲しい
今回は、テレビの音楽番組で半ば日常的に行われてしまっている「当て振り」について、批判的な視点でその背景を紐解くとともに、そんな当て振りをプレイヤー目線で見抜くポイントについてお話しさせていただきました。
当て振り以上に罪深いとされている「口パク」についてもそうですが、こうした「歌ったふり」「演奏したふり」というのは、次のような点において、個人的には大きな問題があると感じています。
- 実際には演奏していないのに、「演奏したふり」をして、視聴者を欺いている
- 楽器演奏を生業としているプロミュージシャンに対して、「演奏したふりをしてください」というのは失礼
- 当て振りを採用する理由のすべてが、制作者側の事情によるものであり、音楽を演奏する者、音楽を聴く者の思いが無視されている
一方で、かつての昭和の音楽番組を見ると、直感的にご理解いただけるように、生演奏特有の揺らぎ、グルーヴ感は格別で、せっかく音楽番組を見るのなら、ぜひこの「ライブ感」を味わっていたいもの。
もちろん、テレビ局や音楽業界を取り巻く厳しい状況からすると、きれい事など言っている場合ではなく、商業的観点から非効率な番組製作をやっている場合ではない…という事情は、一人の社会人として、理解できているつもりです。
でも、そんな時代だからこそ、音楽のおもしろさ、楽しさ、ライブ感をきっちり伝える音楽番組を作り込むことも、中長期的に音楽というコンテンツを持続させる上で、必要になるんじゃないかな…。
少し懐古的、そして情緒的かもしれませんが、昭和の音楽番組の「ライブ感」を知るものとして、そんなことをふと考えさせられた、2021年の年の瀬でした。
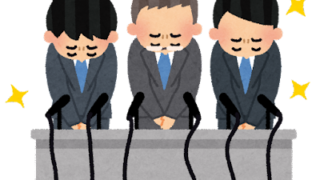

そういったときは、楽器店の下取りに持ち込んでも良いのですが、やはり重たい楽器ともなると、持って行くのも少し面倒だったりするもの。
そんなときにオススメなのが、ネットからも申し込める楽器買取店。
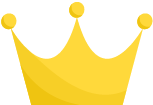 楽器の買取屋さん
楽器の買取屋さん2.ギター買取以外にもベースやギターなどどんな楽器でも買取可能!
3.宅配買取でも送料・手数料完全無料!
電話でもネットでも申し込みができ、最短30分で楽器を現金化できるという圧倒的なスピードが魅力的。
また、査定も楽器のプロが行いますし、全国対応の安心感もあります。
楽器の下取り・買い取りを検討されておられる方、ぜひネットからの楽器下取り・買い取りにチャレンジしてみてください!
| 評価 | |
|---|---|
| 名前 | 楽器の買取屋さん |
| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・全国対応 |
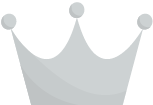 楽器の買取【バイセル】
楽器の買取【バイセル】2.送料無料!箱に詰めて送るだけ♪バイセルの宅配買取
3.楽器以外の時計やブランド品も買取しています。
ギター・管楽器・弦楽器など経験豊富なスタッフがしっかりと状態を確認します。
| 評価 | |
|---|---|
| 名前 | バイセル |
| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・店頭買取 |